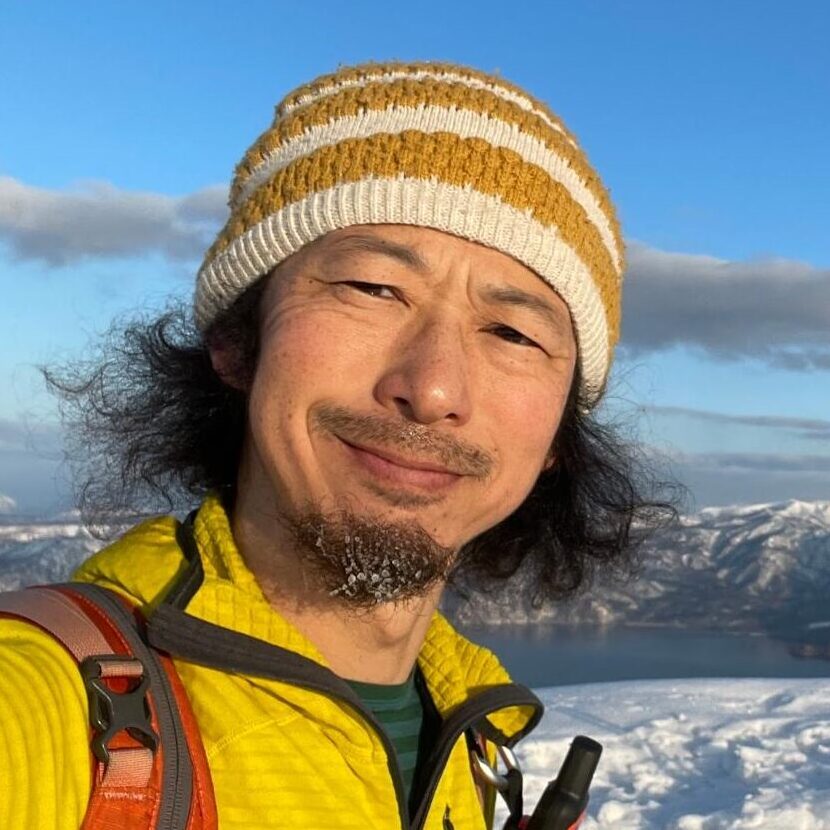沿岸コミュニティ課題
北極沿岸地域の雪氷・海洋・生態系の変化と持続可能な環境―社会システム
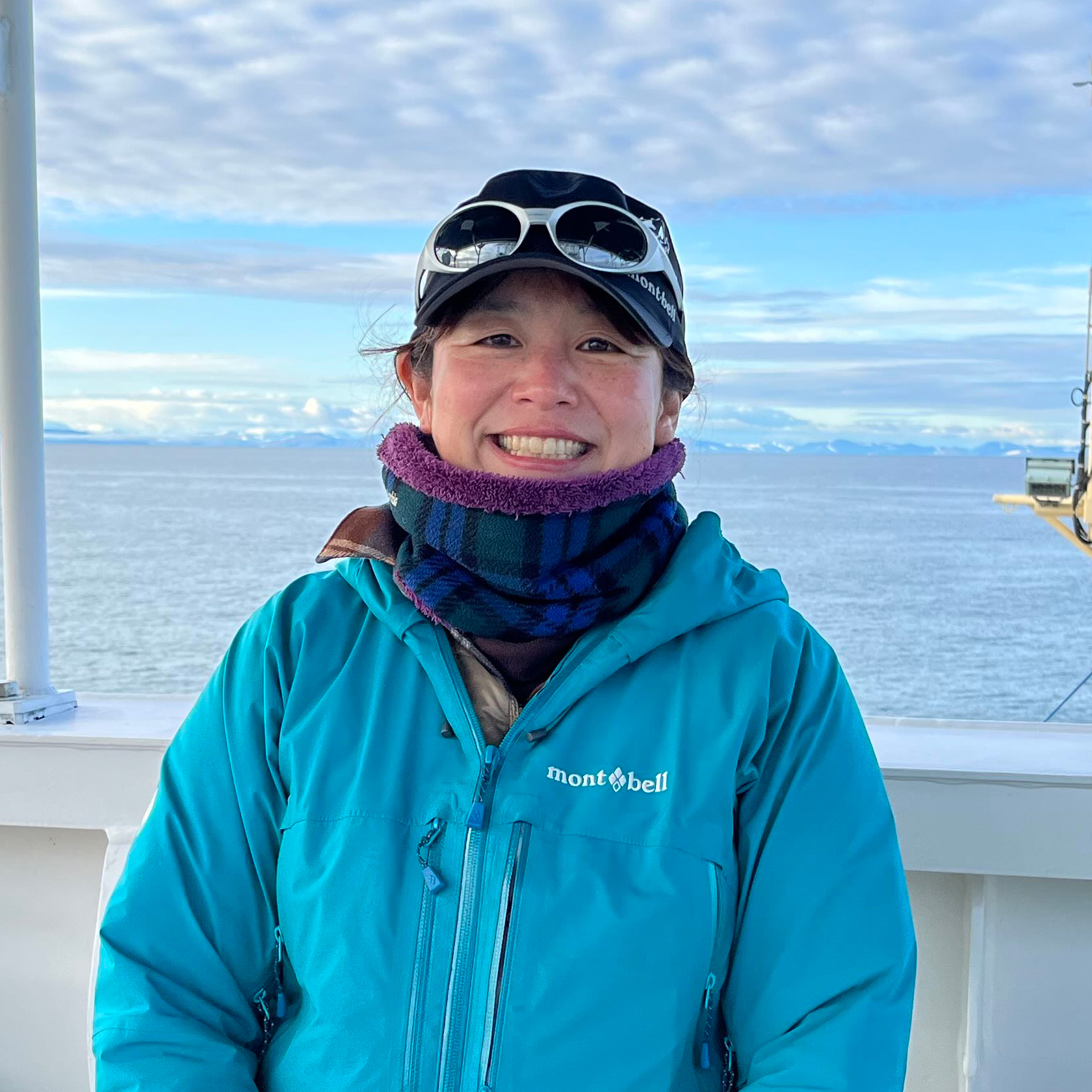
研究課題代表者:三谷 曜子(京都大学)
地球温暖化が急速に進む北極沿岸域では、自然環境と地域社会の双方で深刻な影響が表れており、特にグリーンランド北西部カナック地域では、雪氷の融解や海洋環境の変化が生態系や住民の生活、社会・文化・産業に大きく影響を及ぼしています。これまでの我が国の北極域研究プロジェクトGRENE、ArCS、ArCS IIなどの研究により、氷河と海洋の相互作用、災害リスク、住環境や廃棄物処理の課題、さらに現金収入型の生活への移行や環境劣化への不安といった社会的課題が明らかになってきました。本研究課題は、こうした課題に対応し、北極域の持続可能性向上への貢献を目的とします。
具体的には、衛星データや現地観測を用いて雪氷・氷河・海洋の環境変動を定量的に解明し、その変動が地域社会や住民生活に与える影響を分析します。海洋観測では、水温・塩分、海洋生物の分布調査、鳴音や魚群探知機を用いたモニタリングなどを行い、ホッキョクダラなどの重要種を指標に、生態系内の上下階層のつながりや変動を解明します。また、化学トレーサーやマイクロプラスチック分析を実施し、人間活動による生態系への影響を評価します。さらに地域住民による市民科学を推進し、伝統知や文化を尊重した持続可能な資源利用、防災・減災策、エネルギー効率の高い住環境設計を目指します。
また、本課題は多くの研究課題と連携しながら進められます。生物多様性課題とは汚染物質分析や北海道大学水産学部附属練習船「おしょろ丸」、海洋地球研究船「みらい」による観測連携を行います。先住民課題との協働により、沿岸社会の持続可能性に関する課題抽出と超学際的研究による解決を目指します。また、設置型音響記録計による海洋生物のモニタリングでは、「北極海の利用、氷海変動把握と予測」課題と連携し、北極航路での水中騒音問題に取り組みます。エアロゾル課題とは氷河・氷床変動の定量化やメカニズム解明を進めます。さらに歴史課題やガバナンス課題との連携により、海棲哺乳類利用の歴史や国際保全管理の整理を通じ、食の主権や食料安全保障に貢献します。気候災害課題とは地滑りや洪水、津波災害に関するデータ共有を行い、陸域人間圏課題とは室内環境や災害対策において協力します。これらの連携を通じ、カナック地域を北極のモデルケースとして、地球温暖化がもたらす自然環境と地域社会の複雑な相互作用を総合的に解明し、北極域と日本社会双方の持続可能性向上に資する知見を提供します。
サブ課題代表者
-
 富安 信(北海道大学)
富安 信(北海道大学) -
 植竹 淳(北海道大学)
植竹 淳(北海道大学) -
 東條 安匡(北海道大学)
東條 安匡(北海道大学) -
 三谷 曜子(京都大学)
三谷 曜子(京都大学)
海外連携機関
グリーンランド天然資源研究所
メンバー
| サブ課題1 | |
|---|---|
| 氏名 | 研究機関 |
| 富安 信 | 北海道大学 |
| 山口 篤 | 北海道大学 |
| Thiebot Jean–Baptiste | 北海道大学 |
| 長谷川 浩平 | 北海道大学 |
| 小川 萌日香 | 国立極地研究所 |
| 大槻 真友子 | 北海道大学 |
| 松野 孝平 | 北海道大学 |
| 野村 大樹 | 北海道大学 |
| 向井 徹 | 北海道大学 |
| 佐々木 貴文 | 北海道大学 |
| 松田 純佳 | 北海道大学 |
| 油島 明日香 | 北海道大学 |
| 山野 将輝 | 北海道大学 |
| 辻村 匠真 | 北海道大学 |
| サブ課題2 | |
|---|---|
| 氏名 | 研究機関 |
| 植竹 淳 | 北海道大学 |
| 杉山 慎 | 北海道大学 |
| 西村 基志 | 信州大学 |
| 渡邊 達也 | 北見工業大学 |
| Podolskiy Evgeny | 北海道大学 |
| 今津 拓郎 | 北海道大学 |
| 矢澤 宏太郎 | 北海道大学 |
| 見米 富視 | 北海道大学 |
| 中山 智博 | 北海道大学 |